経営者向けの本ではなく、全ての知識労働者必読のセルフマネジメント
本書は企業経営者だけでなく、全ての知識労働者に向けて書かれた、セルフマネジメントの本です。
「経営者の条件」という邦題ですが、原題は”The Effective Executive”です。
本書ではエグゼクティブとは知識労働者全てのことを指します。今日は多くの仕事が知識労働となっているので、ほとんどの方が対象となります。 そして、エグゼクティブとして成果をあげるためには、どうあるべきかが説かれています。 自らをマネジメント出来ないものが、組織をマネジメント出来るわけがありません。
原書は1964年に書かれたものですが、内容は今でも非常に有効な内容だと思います。様々な自己啓発やビジネススキル関連の書籍の内容が、この一冊にまとまっていると言えます。
以下が成果をあげるための条件として挙げられます。
- 時間を体系的に管理する
- 「仕事」ではなく、期待される「成果」に焦点を当てる。
- 自らの「強み」。上司・同僚・部下の強みを基盤とする。
- 優れた仕事が際立った成果をあげる領域に集中すること。
- 成果をあげる意思決定を行うこと。
1.時間管理は、まず自分自身の時間がどう使われているのかを知ることの重要性、そして、時間把握の方法について語られています。
2.「成果」に焦点をあてる点においては、知識労働者のほとんどが専門家である点を踏まえ、その専門性が統合された上で成果に結びつくため、自らの専門性だけでなく、知識全体の中で、どう位置づけられるのか、自身のアウトプットがどう成果に貢献出来るのかを意識することが重要性であると説いています。
3.「強み」を基盤とする上では、自身の強みを踏まえた成果への貢献を考えることはもちろん、組織として、どう人材を配置すべきかといった組織的視点での展開もなされており、人事・HRMの点でも基本的な考え方として参考になります。
4.「集中」については、1.の時間管理からも繋がりますが、「劣後順位」を決めることが重要であると説かれています。つまり、何をするかではなく、何をしないかを決める。「真に意味あること・重要な事は何か」を決めることが重要。
5.「意思決定」では、意思決定における一連のステップを挙げ、それぞれにおける重要なポイントを抽出。
- 問題の種類を知る
- (課題解決・成果に結び付くための)必要条件を明確にする
- 何が正しいかを知る
(妥協はあるとしても、受け入れられやすい妥協案から考えてはいけない) - 行動に変える
(【その意思決定を誰が知り/どのような行動が必要で/誰が行動をとり/その行動はいかなるものであるべきか】が重要) - フィードバックを行う
これを踏まえて、成果を上げるための意思決定とはどうあるべきか。「意見の不一致がない場合には意思決定しない」など、ここには所謂クリティカルシンキングのような考え方が説かれていると理解しました。
そのタイトルから、敬遠というか、後回しにしていたのですが、本書は全てのビジネスパーソンに必要な要件であると考えます。訳者上田氏もあとがきで書かれているように、「できる人」になるための条件が本書には詰まっています。 新社会人の方も含めて、全てのエグゼクティブ(知識労働者)におすすめです。
| ドラッカー名著集1 経営者の条件 | |
 |
P.F.ドラッカー
ダイヤモンド社 2006-11-10 おすすめ平均 |
ピータードラッカーと言えば、経営学の権威ですが、本書は上述の通り、企業経営や組織管理についてではなく、自分自身、個人のマネジメントについて書かれています。
自身もいずれは読まなければと思いつつ、後回しにしていたのですが、本書はもっと早い時期、社会人になったらすぐにでも読んでおくべき本だったなと思います。
日本は製造業の生産効率をとことん高め成長してきましたが、一方で日本のホワイトカラーの生産性は先進7カ国の中でも最下位、OECD加盟国の中でも30カ国中20位(2009年度版 労働生産性の国際比較:生産性本部)となっています。労働生産性とは、労働力(単位時間当たりの労働投入)に対してどれだけの価値を生むことができたか。
ホワイトカラー、所謂、知識労働者にとってこの価値というのが、目に見えにくい。働いた時間の分だけ、価値が生み出せるとは限らないからです。それは決して、企画部門やアイデアを出す部門に限りません。経理や法務、人事部門などの管理部門はもちろん、営業部門なども同様です。また、こうして企業や組織が大きくなり、成果を生み出すための役割分担や機能が分かれてくると、ますます見えにくくなってきます。
自身が以前大企業に勤めていた時、その企業では事業部制の組織構造を取っていました。いわく、収益をあげる事業部がプロフィットセンターであり、経理や法務、人事などのコストセンターがあると考えていましたし、一般的にはそういう理解であっていると思います。しかし、ドラッカーは本書で以下のように述べています。
「組織の内部に生ずるものは、努力とコストだけである。企業にはプロフィットセンターがあるかのごとくいわれるが、単なる修辞にすぎない。企業には“努力センター”があるだけである」
企業のどの組織・部署であろうと、生産性を高めることが求められます。それも成果に繋がる行動を行っていく必要があります。昨今では、収益だけではなく、企業の掲げる理念やビジョンの実現に結び付くかどうかという視点、社会貢献・CSRの視点も重要になってくるでしょう。
知識社会・情報化社会と言われて久しいですが、未だにその生産性向上については課題があります。企業側・上司や組織上の問題も多分にありますが、それ以前に、自らの生産性を高め、将来的には、生産性の高い組織作りを行っていけるような人材になるうえでも、本書はお勧めです。
また、これまで、いろいろな自己啓発関係の書籍も読んできましたが、その集大成と言っても過言ではないかと思います。



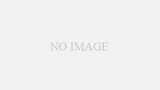
コメント